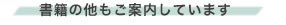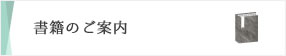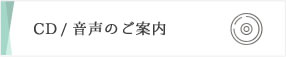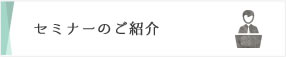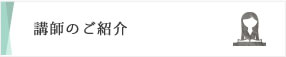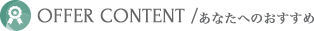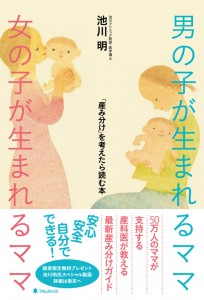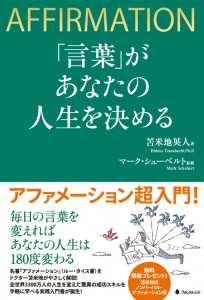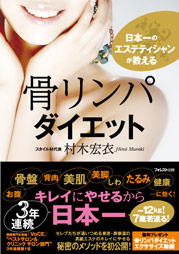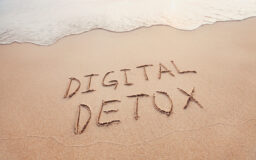パラベンというのは、化粧品に入っている防腐剤の一種です。日本では、長年、化粧品の品質を保つために使われてきました。
しかし、人によっては肌トラブルを起こす可能性があったり、毒性のある添加物として認識されていたりと、何となく悪いイメージを抱いて避ける人も少なくありません。
そんなイメージを受けて、化粧品の中には「パラベンフリー」と表示して、パラベンが入っていないことを売りにするものも増えています。
しかし、実際のところ、その真偽はどうなのでしょう。本当にパラベンは避けた方が良い物質なのでしょうか?それとも心配せず使って良いのでしょうか?
その効果と注意点を正しく知った上で対処できるよう、これからパラベンの安全性や人体への影響、パラベンフリーの知られざる事実などについて詳しくみていきましょう。
目次
2. パラベンとは何か
2-1. 化粧品によく使われるパラベンは、5種類
2-2. 少ない配合量で、高い効果が期待できる
2-3. パラベンは適応力も高いため重宝される
3. パラベンはなぜ避けられがちなのか?
3-1. 「表示指定成分」が生んだ誤解
3-2. 人体への危険性はどの程度あるのか
5. パラベン以外でよく使われる防腐剤
5-1. フェノキシエタノール
5-2. 1,3-ブチレングリコール(BG)
5-3. アルコール
5-4. その他の防腐剤
1. なぜ化粧品に防腐剤が必要なのか

防腐剤とは、その名の通り化粧品が腐ってしまわないために使用されています。まず知っていただきたいのは、化粧品も時間とともに劣化するという事実です。
まず、私たちの手に渡る前の段階で、工場で生産され、運ばれている間、店に並んだ後、など何日かかるか分かりませんし、品質を左右する温度が一定とは限りません。
そしてさらに注意したいのは、私たちが使い始めてからの管理の問題です。日光や温度による劣化、手指を介して入る雑菌、空気に触れて起こる酸化など、身近な原因で化粧品の品質は変わってしまいます。特に水性成分の中は雑菌が繁殖しやすく、腐ったり、カビが生えたりと変質しやすいのです。
これをできる限り防ぐために、市販品はほとんどの場合、防腐剤が添加されています。逆に、防腐剤を使わないと品質が不安定になりやすく、私たちのお肌にとってはかえって危険になるという面もあるのです。
そして、このときに化粧品の防腐剤としてよく使われているのが、パラベンなのです。
2. パラベンとは何か

パラベンは、正式名称をパラオキシ安息香酸エステルといいます。製品の成分には、この名称で書いてある場合もあります。
人体に対する毒性が低く、微生物やカビなどの菌類を排除するのに効果的なので、化粧品や医薬品によく使用されています。
殺菌力が強いものから弱いものまで、パラベンの中にもいろいろ種類があり、総称して「パラベン類」といいます。
2-1. 化粧品によく使われるパラベンは、5種類
殺菌力の高い方から順に並べると、
イソブチルパラベン>ブチルパラベン>プロピルパラベン>エチルパラベン>メチルパラベン
となります。
それぞれどの微生物や菌に強いか、水に溶けやすいか油に溶けやすいかなど、得意不得意が多少違います。そのため、一種類だけを使うのではなく、大抵は数種類のパラベンを組み合わせて使い、殺菌効果を高めます。
ヨーロッパでは、複数のパラベンをある効果的な比率で混ぜた、「パラベンカクテル」が化粧品の原料として使われています。
日本で化粧品によく使われるのは、エチルパラベンやメチルパラベンです。パラベンの中では効果が穏やかな分、肌への刺激も少なく安全性が高いので、医薬品や食品の保存料としても使われています。
2-2. 少ない配合量で、高い効果が期待できる
厚生労働省が定める「化粧品基準」というものがあります。薬事法に基づくもので、化粧品に使われる成分の、配合上限などが記されています。
この基準によるパラベンの配合率上限は、1%(100gに対して1.0g)です。実際に市販されている化粧品では、ほとんどの製品において0.1~0.5%という低めの配合率になっているようです。
他の防腐剤だと、もっと高い配合率でないと効果を発揮しないものも多くあります。
パラベンは少ない量で確かな効果が期待できるという強みがあります。
2-3. パラベンは適応力も高いため重宝される
パラベンは、アルカリ性のものに配合されても、酸性のものに配合されても、変わらず効果を発揮します。
効果が高いだけでなく、さまざまな製品への配合が可能なため、重宝されているのです。
3. パラベンはなぜ避けられがちなのか?

少量で効果がある上に、食品にも使用される毒性の低いパラベン。
多くの製品に使われるのも当然のことでしょう。ところが、私たちは「パラベンフリー」の表示をよく目にしますよね。
これは、パラベン不使用をうたって、安全を強調しているという意味です。
数ある防腐剤の中で、なぜパラベンだけが悪者のように避けられているのでしょうか。
3-1. 「表示指定成分」が生んだ誤解
ことの発端は、1980年に、厚生省(現厚生労働省)定めた「表示指定成分」というものです。
これによって、体質によってはアレルギーなどの皮膚トラブルを起こすおそれがある103種類の成分を化粧品に配合するとき、その成分名をパッケージに記載することが義務づけられました。そして、パラベンも、この表示指定成分に含まれたのです。
ところがこの指定成分は次第に「体に悪影響を及ぼす毒性が強いもの」と誤った認識をされるようになったのです。
本来、アレルギー症状が起こる人のみ避ければいいものが、すべての人が避けたい成分のようなイメージすり替わってしまったのです。
分かりやすく食品で例えると、本来3大アレルゲンの一つである卵が含まれる製品は、卵アレルギーの人が摂取を控えますが、誤った認識により、卵という表示があることですべての人がその製品を食べなくなってしまう、というイメージなのです。
そして、防腐剤としてよく使われるパラベンは、表示される機会も多く、「パラベンフリーの表示は安全性の高い製品という意味」などと誤った印象を強く持たれてしまうことになったのです。
さらに、「表示指定成分さえ入っていなければ安全」という勘違いも生まれました。人によっては、指定成分以外のものでアレルギーを起こすこともあります。
そこで、特定の成分だけを表示するこのやり方は2001年に廃止され、代わりに、化粧品に配合されている全成分の名称を表示する「全成分表示」が義務になりました。
しかし、現在でも、パラベンなどに対する誤解が解けたとは言い難い状況が続いています。
3-2. 人体への危険性はどの程度あるのか
人によっては肌が荒れるというアレルギー反応の他に、パラベンには危険性はないのでしょうか。
実験により、高濃度のパラベン溶液を人の肌に直接塗ったり、ウサギに点眼したりした場合などに、わずかな刺激があったという報告は、何件か確認することができます。
しかし、薄めた溶液を繰り返し塗ってみる、というような実験では、刺激はほとんどみられないということです。
2004年には、パラベンが乳がんを誘発するのではないかという医師の報告が注目されましたが、これには反論も多く寄せられ、確証には至っていません。
パラベンは危険だ、という声は定期的にあがりますが、それを強く裏付ける実験結果はないのです。
4. パラベンフリーは、防腐剤不使用という意味ではない
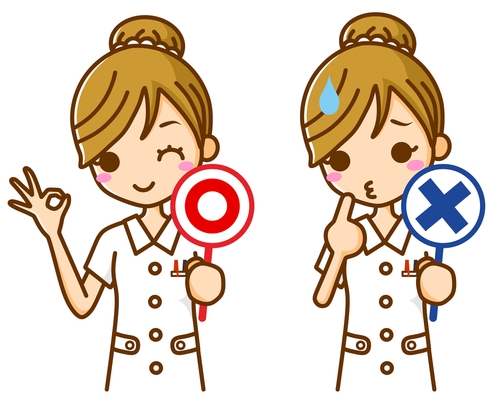
事実はどうあれ、悪者のイメージがついてしまったパラベンを避けようとする人は多いものです。
そこで化粧品を作るメーカーは、パラベンを使わずに品質を保持する配合を考え、パラベンフリー(パラベン不使用)と表示した商品を出すようになりました。
もちろん、本当にパラベンでアレルギーが出てしまう人にとっては、良い傾向です。でも、「何となくパラベンフリーの方が安全な気がする」と感じるなら、要注意。
パラベンフリーの化粧品は、あくまでもパラベンが配合されていないということで、防腐剤が入っていないわけではありません。
最初に説明した通り、化粧品は雑菌が繁殖しやすいものです。特に家庭では大抵常温保存するので、細菌の温床になります。
これを防ぐためには防腐剤が必要で、パラベンフリーの化粧品でも、別の防腐剤が配合されていることがほとんどなのです。
5. パラベン以外でよく使われる防腐剤

パラベンが使用されない場合、どんな成分を配合して化粧品の腐敗を防いでいるのでしょうか。
これから、パラベン以外でよく使われる防腐剤を見てみましょう。
ただし、これらのどの防腐剤にも言えることは、単独で大量に混ぜられることはほぼないということです。基準に沿って、安全な規定量内に抑えられています。
5-1. フェノキシエタール
パラベンの代わりになる防腐剤として、パラベンフリーの化粧品によく使われています。緑茶由来の成分なので、天然由来=安全というイメージがあるかもしれません。
ですが、パラベンより殺菌力が劣るため、単独で配合する場合はパラベンの約3倍の配合量が必要となります。また、配合率が4%以上になると、皮膚への刺激となることが分かっています。
5-2. 1,3−ブチレングリコール
乳液やクリームなどによく用いられる成分です。
単体で防腐効果を高めるには10%以上の配合が必要になるため、この成分でかぶれる人もいるようです。
成分表示上、1.3BGと略して記されることもあります。
5-3. アルコール
化粧品に使われるのは、飲料にも含まれる「エチルアルコール」です。
成分表示上は「エタノール」と記載されます。
肌を引きしめる収斂効果など複数の効果があり、化粧品によく配合されていますが、防腐剤としての効果を出すには10%以上の配合が必要です。
アルコールに弱い人は、これでかぶれることがあります。
5-4. その他
他にも、安息香酸Na、デヒドロ酢酸Na、ヒノキチオールなどが、防腐剤としてよく使われます。ヒノキチオールはヒノキ由来の、殺菌力の高い植物成分です。自然なイメージのある名前なので、防腐剤不使用をうたう製品に使われたりします。
6. パラベンの化粧品以外への使用
パラベンが使われているのは、化粧品だけではありません。たとえば医薬品。1924年に初めて医薬品の防腐剤として使用され、今も多くの医薬品に配合されてきています。
また、食品にも保存料として使われています。
日本ではエチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルパラベンなどが、醤油や酢、清涼飲料水などの特定の品物についてのみ、配合が認められています。配合できる量も厳密に決まっています。
このようにパラベンは、化粧品に限らず、私たちが口にする薬や食品の腐敗も防ぎ、時間が経っても安全に摂取できるよう保ってくれているのです。
まとめ

パラベンは防腐剤の中でも、比較的、低刺激で安全に使える成分です。
私たちが何となく避けた方が良いように思ってしまうのは、かつて表示指定成分として記載され続けた影響だったのです。
化粧品を長期にわたって、安定した品質で使用するために、防腐剤の配合は必要不可欠だといえます。
むしろ、私たちが一度購入した化粧品を数ヶ月以上使い続けられるのは、パラベンを代表する防腐剤のおかげと言っても過言ではないのです。
ごく稀にアレルギー反応の出る人はいますが、そうでない人は、「パラベンフリーであるかそうでないか」を気にすることなく、安心して自分の好みの化粧品を使ってくださいね。
【参考資料】
『ウソをつく化粧品』 小澤貴子 フォレスト出版 2015年
『医師・医療スタッフのための化粧品ハンドブック』 平尾哲二 中外医学社 2016年
『化粧品成分表示のかんたん読み方手帳』 久光一誠(監修) 永岡書店 2017年