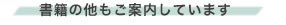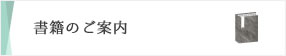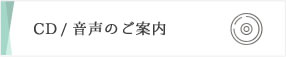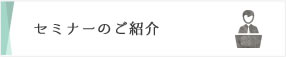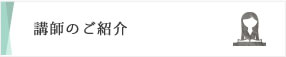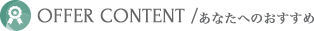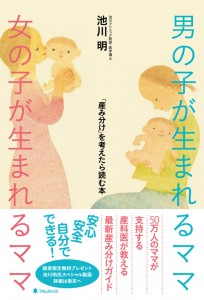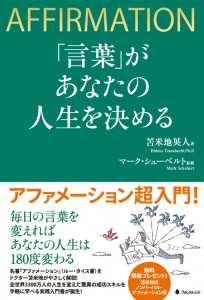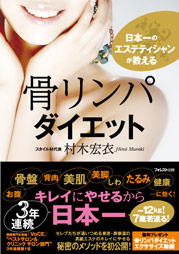あなたには、必ず「ほかの人にはない」何かがあります。そしてその「違い」こそが、誰かから必要とされる「価値」となりうるものなのです。
あなたが提供したいと思っている商品やサービスは、誰かに求められているものかもしれません。しかし大抵の商品やサービスは、すでに世の中にあるものです。あなたが提供するものとそれらとの違いが判らなければ、価格競争や宣伝競争に巻き込まれてしまうでしょう。
例えば、あなたが1本70円で仕入れたペットボトルのミネラルウォーターを、100円で売るとしましょう。あなたのお店に買いに来てくれる方や、送料を払って注文してくれる方が、あなたのお客さまになります。
ところがそのミネラルウォーターは、自動販売機やコンビニ、スーパーやネットでも売っています。
今すぐに冷えたミネラルウォーターが欲しい方は、110円で売っている自動販売機やコンビニで買うかもしれません。割高だったとしても気軽に必要な時に買えるからです。また安く買いたい方は特売チラシを見て、80円で売っているスーパーに行くかもしれませんし、まとめ買いしたい方は、送料無料で配送してくれるネットで買うかもしれません。
このように、より規模が大きな企業と同じ商品やサービスを提供しても、個人の起業家が太刀打ちするのは難しいですよね。
『新版 小さな会社☆儲けのルール』を書いた零細企業コンサルタントの栢野克己氏は、“「何かでナンバーワンになることを目指す」これが、小さい会社の経営が安定し、成功する最短の道です。”と説き、自分の街の特定の客層や年代、もしくは友人知人の中でも、小さな年商でいいからナンバーワンになれるものを探すことが大事だと説きます。
また『あなただけのオンリーワンメニューのつくり方』を書いたマーケティングコンサルタントの穂口大悟氏は“あなたの商品やサービスが「ほかのものとは違う」と一目で判るなら、それを必要としているお客さまの目に留まりやすくなり、選ばれやすくなる”と語り、スモールビジネスの「非競争マーケティング」を提唱しています。
この記事では、起業している、またはしようとしている「あなただからできる」「ほかにはない何か」を洗い出し、それを具体的な商品やサービスの形にして、世の中に広めるための3ステップについてお伝えします。
目次
1. 「わたしだから」な起業に向かって、過去・現在・未来を見渡してみる
1-1. 【過去】成功したことを思い出して商品やサービスを考える
1-2. 【現在】業界・市場×商品・サービスのマッチングを行う
1-3. 【未来】「わたしだから」な起業の成功ビジョンを描く
2. 「わたしだから」を形にした商品やサービスをつくる
2-1. わたしのお客さまが持っている願望や悩みを見つける
2-2. 自分と商品やサービスの強みを棚卸する
2-3. お客さまの願望や悩み×自分の強み=「わたしだから」な商品やサービスの素
2-4. 「テレビショッピング方式」の紹介文でお客さまの背中を押す
2-5. 理想の金額と気持ちよく払える金額のバランスをとる
2-6. お客さまや自分にしっくりくる名前をつける
2-7. 自分の基地に必要な情報をアップする
3. 「わたしだから」できるお役立ちを、ブログで発信する
3-1. 見返りを求めない記事でお客さまの心をつかむ
3-2. 4つの切り口からテーマを考える
3-3. 5ステップの構成で書く
3-4. SNSでシェアする
1. 「わたしだから」な起業に向かって、過去・現在・未来を見渡してみる

1-1. 【過去】成功したことを思い出して商品やサービスを考える
まずは、過去を振り返ってみましょう。
2002年に初版が出て以来、息長く売れ続けて10万部を超えるベストセラーとなっている『新版 小さな会社☆儲けのルール』で、零細企業コンサルタントの栢野克己氏は「あなたの天職はなんですか?」と問いかけます。独立に際して、扱う商品やサービスの内容は何にするか、何をして食べていくか。これが、最初に決めるべきことだということです。
あなたの天職を考えるために、まずは過去にやってきたことの中で、好きだったこと、得意だったことを思い出していきます。
例えばつぎのような項目に沿って、書き出してみてもいいでしょう。
・前の仕事で何をどのくらいの期間やっていたか
・その中でどの仕事がいちばん好き・得意だったか
・成功したり、称賛されたりしたことは何か
・どんな商品やサービス、お客さまが好きだったか
この中から、自分が好きだったり得意だったりすることや、好きなお客さまに向けた商品やサービスで起業することが、成功率を高めるポイントです。
なお、今までに経験がある商品やサービス、顧客層とは異なることで起業すると、失敗する確率が高いと言われています。前職での商品やサービス、お客さまを引き継ぐことができる方は、まずはそこから始めることをお勧めします。
自分が提供したいと思う商品やサービスが見つかったら、現在に戻りましょう。
1-2. 【現在】業界・市場×商品・サービスのマッチングを行う
それでは、現在を眺めてみましょう。
前項で考えた商品やサービスを前提に、どのような業界や市場に提供していくかをイメージしていきます。
ここで注意してほしいのが、商品やサービス、顧客層がこれから伸びる、人気があるといわれている将来性のありそうな業界や市場は、避けたほうが無難だということです。そのような業界や市場は、資本力がより大きな企業も目をつけやすいため、規模の競争となる可能性が高いからです。あえて市場規模が小さなところを狙うほうがよいでしょう。
個人起業でお勧めなのは、手がかかるために大手が扱えないローテクな商品やサービスです。例えば一点ものの服や雑貨、書籍を組み合わせて少量多品目に扱うことや、占い×アロマテラピーのようにユニークな組み合わせのサービスを提供することも考えられるでしょう。
ひとつひとつはすでにある商品やサービスでも、あなたが好きなこと、得意なことを複数かけ合わせれば、ほかにはないオリジナルなものを生み出せる可能性が高まります。
提供する業界や市場のイメージができたら、未来へと向かいましょう。
1-3. 【未来】「わたしだから」な起業の成功ビジョンを描く
それでは、幸せな未来を想像してみましょう。
商品やサービスを開発し、世に出した5年後のあなたは、どんな毎日を送っているでしょうか。ひとりで、パートナーや家族と、あるいはスタッフや仲間と、どんな場所で過ごし、どのようなお客さまに対して、どんな商品やサービスを提供しているでしょうか。
あなたは未来にいます。すべての制限を取り払って、自由に思いのままに、つぎの4項目にそってイメージをふくらませてみましょう。
・誰と
・どこで
・どのようなお客さまに
・どのような商品やサービスを提供しているか
十分にイメージができたら現実に戻ってきてください。
そして、わたしだからできる、ほかにはない商品やサービスを具体化させていきましょう。
2. 「わたしだから」を形にした商品やサービスをつくる

2-1. わたしのお客さまが持っている願望や悩みを見つける
まずはあなたにとって大切なお客さまを、ひとりだけイメージしてみましょう。
実際にいるお客さまや、身近な家族・友人などをモデルにしてもいいですし、キャラクターを考えるように、あなたがこんな人に来てほしいと思うお客さまをイメージしてもいいでしょう。イメージをふくらませながら、年齢や家族構成、日々の生活や関心を持っていることなど、その人のプロフィールを具体的に書き出していきます。
お客さまのプロフィールができたら、そのお客さまがどんな願望や悩みを持っているのかを考えてみましょう。
例えば、47歳のパートタイムで働いている主婦で、息子が大学に行っている母親であれば、
・最近始めたヨガが楽しくなって、インストラクターを目指している
・更年期症状が出てきて、心身の状態が不安定だと感じている
・息子の学費が大きくて、経済的に負担がある
のように、原因とそれによって引き起こされている願望や悩みを5つ以上書き出していきます。
2-2. 自分と商品やサービスの強みを棚卸する
つぎに、自分の強みを棚卸ししていきます。
・自分の強み
・商品やサービスの強み
・商品やサービスを提供する方法の強み
の3つの角度から考えていきましょう。
強みはできるだけ具体的に書き出すのがポイントです。例えばつぎのように数字を入れたり、具体的な内容を入れたりするとよいでしょう。
・数字を入れる
例「課長として活躍した」
↓
「女性中間管理職として2年間、15名の部下とともに新規プロジェクトを立ちあげ、1億の売上を達成して社内表彰を受けた」
・具体的な内容を入れる
例「コーチングの資格を持っている」
↓
「カウンセリングやコーチング、アロマテラピー、フラワーレメディなどを学び、ビジネスからスピリチュアルまで幅広い方に対応したセッションができる」
こちらも、項目ごとに3つ以上を目標にして書き出してみましょう。
2-3. お客さまの願望や悩み×自分の強み=「わたしだから」な商品やサービスの素
お客さまの悩みと自分の強みが書き出せたら、悩みと強みをかけあわせて、商品やサービスの素をつくっていきます。
まずは、縦軸にお客さまの悩み、横軸に自分の強みを書いた分析シートを作ります。そして、悩みと強みの重なったところに、お客さまの悩みを自分の強みで解決する方法を書き出していきます。
・願望:最近始めたヨガが楽しくて、インストラクターを目指している
・強み:コーチング
のマスであれば「資格を取ったらやりたいことを深堀し、達成をサポートする」となるかもしれませんし、
・悩み:更年期症状が出てきて、心身の状態が不安定
・強み:アロマテラピー
のマスであれば「更年期症状に特化したアロマテラピーの施術を提案する」となるかもしれません。
まずはマスを埋めながら、それが本当にやりたいと思うアイディアか、提供する商品やサービスに心からワクワクするか、ということを確かめていきましょう。そのうえで、つぎの3つの視点から、難しいと判断したものは省いていきます。
・本当にやりたいアイディアか
どんなに有望なアイディアでも、それを提供することが楽しいと思えなければ、売れれば売れるほど苦しくなってしまうでしょう。
例えば『新版 小さな会社☆儲けのルール』には、うつ病専門の社労士の方のエピソードが載っています。一般的にはやりたいと思う社労士さんが少ないために、成功したという好事例ですが、この場合、うつ病の方の支援に強い意欲をお持ちの方であれば、それこそが天職となるでしょうし、単にニッチを狙って始めたとしたら、続けていくうちに苦しくなるかもしれません。
本当にやりたい、ワクワクする!というアイディアだけを残していきましょう。
・手持ちの資本やスキルで実現できるか
例として「更年期症状に特化したアロマテラピーの施術を提案する」というサービスが浮かびましたが、もしあなたが更年期症状についてよく知らなければ、新たに更年期について学んだり、新しい技術を身につけたりする必要があるでしょう。そのように、実現に時間がかかりそうなアイディアはいったん横において、すぐに商品やサービスとして使えそうなアイディアから検討します。
ただし、それがどうしてもやりたいと思うことであれば、起業のタイミングをずらして、そのアイディアの実現に取り組むのもひとつの方法です。
・お客さまに受け入れられるか、奇抜すぎないか
『あなただけのオンリーワンメニューのつくり方』には“「不倫の恋に悩む方のためのカウンセリング」という表現では、自分のお客さまがひいてしまうかもしれない”という事例があげられています。来てほしいと思うお客さまがどのような感覚の持ち主なのかをしっかりとイメージして、自分のお客さまにとって受け入れやすい商品やサービスを選んでいきましょう。
3つの視点をパスした商品やサービスを、一度に扱いきれる数にまで絞り、残りのアイディアは次の機会に取り置きます。
それでは出そろった素を、具体的な商品やサービスの紹介文に仕上げていきましょう。
2-4. 「テレビショッピング方式」の紹介文でお客さまの背中を押す
わたしたちが商品やサービスを購入するときには「注意をひかれて」「興味をもって」「ほしくなって」「(買うという)行動を起こす」という流れがあります。これをマーケティングの用語で「AIDA(アイダ)」と言います。
商品やサービスを提供するときにこのAIDAを活用すると、よりお客さまの気持ちに寄り添いながら案内をすることができます。『あなただけのオンリーワンメニューのつくり方』で例としてあげられている、テレビショッピングの例を見てみましょう。
A(注意):「レンジフードが油汚れでべとべと」「お風呂の隅がカビで黒ずんでいる」のように、お客さまが困っていることを列挙し、問題点をあげて注意をひきます。
I(興味):問題点の根本原因を伝えます。「汚れが落ちないのは、ミクロの隙間に入り込んでいて、上からこすっても届かないから」というように、原因を知ることにより、興味を芽生えさせます。
D(欲求):ここですかさず、商品説明に入ります。問題の根本原因を解決する、新たな機能が解説されます。「宇宙開発の技術を応用した〇〇ポリマーが、ミクロの隙間から汚れを掻き出す!」というような、ややオーバーアクションな解説が購入意欲を刺激します。
A(行動):画面に電話番号をはじめ「返品可能」「数量限定」「特典つき」などの注文を後押しする情報が流れ、電話をかけるという行動に向けて背中を押します。
それでは、このテレビショッピング方式で「わたしだから」な商品やサービスの素を仕上げていきましょう。
A:(問題や悩みで注意をひく)お客さまの願望を妨げる問題や、悩みを例としてあげて注意をひきます。ここでは、より具体的な「あるある」というパターンを考えます。
↓
I:問題や悩みの一般的には知られていない根本原因を伝えます。専門家だからこそ伝えられる「なるほど!」というレベルまで掘り下げ、共感とともに伝えます。
↓
D:問題や悩みの根本原因を解決する方法を、解説します。お客さまの目線で、どのような流れで問題が解決するのかを伝え、疑似体験をしてもらいます。
↓
A:注文を後押しする情報を伝えます。具体的な過去のお客さまの事例や、自身のエピソードを交えながら、お勧めするための一言を添えます。
あなたが前項で作った素を、このAIDAの流れに乗せて考えながら、商品やサービスを紹介する文章を作り上げましょう。
これで、お客さまに提供できる商品やサービスが出そろいました。最後に商品やサービスの金額と名前を考えましょう。
2-5. 理想の金額と気持ちよく払える金額のバランスをとる
提供する商品やサービスの金額を決めていきます。すでにある商品でも、仕入れ値と定められた希望小売価格との間で自由に決められるケースもあるでしょうし、サービスやオープンプライスな商品であれば、一から自分で決めていく必要があるでしょう。
金額は、継続していくために必要な金額から割り出した理想の金額と、同じ、もしくは類似した商品やサービスの金額とを鑑みながら、お客さまが気持ちよく支払える料金のバランスをとることが必要となります。
告知する当初から適正な金額にできれば一番ですが、実際にはお客様のフィードバックを鑑みて、バランスをとることが多いです。
2-6. お客さまや自分にしっくりくる名前をつける
すでに名前が決まっている商品以外については「誰のために」「どんな悩みを解決したり願望を実現したりするために」「何を提供するのか」という観点から考えます。自分の大切なお客さまにとって、受け入れやすい商品やサービスの名前をつけましょう。
また、自分というパーソナルスタイルも大切です。『新版 小さな会社☆儲けのルール』では、葛飾区にある1坪で1億円の売上を誇る惣菜店「かねふじ」の、社長の例が紹介されています。
ぽっちゃりとした体型で、明るくよく笑う社長は繊維機械のエンジニアでしたが、機械相手は面白くないと思って転職したという、女性受けする人柄です。対する著者の栢野氏は、アゴが張った人相で、気難しく愛想が悪いタイプ。物理や発明もの、機械が好きで、コンサルでも、製造業や卸売業を相手にするのが得意だと言います。
このように自分の顔や性格、好き嫌いから見出せる「パーソナルスタイル」と商品やサービスの名前のテイストがマッチしていることは、意外と大切です。
2-7. 自分の基地に必要な情報をアップする
提供する商品やサービスが完成したら、ホームページなどにアップしましょう。
あなたのプロフィールや起業のコンセプト、お客さまの声、注文・予約フォーム・手段の案内、そして必要に応じて所在地や地図、メルマガ登録のフォームなどがあるとよいでしょう。
ホームページを持たない方も増えてはいますが、企業などでは社会的な信用の有無や認知度を、ホームページの有無やその内容ではかるケースも多くみられます。どのようなお客さまや取引先との関係があるかを鑑みて、ウェブに関する方針を判断するとよいでしょう。
3. 「わたしだから」できるお役立ちを、ブログで発信する

3-1. 見返りを求めない記事でお客さまの心をつかむ
商品やサービスを、ホームページなどにアップしたら「わたしのお客さま」の悩みを解決する記事をブログで発信しましょう。見返りを求めずにお役立ち情報を提供していくことで、あなたへの信頼が高まり、その商品やサービスを必要とするお客さまが訪れるようになっていきます。
お役立ちブログは、つぎの手順に沿うとスムーズに書けるでしょう。
3-2. 4つの切り口からテーマを考える
毎日、一から考えるのは大変なので、先に1か月分程度のテーマを出しておくのがお勧めです。商品やサービスからお客さまの悩みを想定していきましょう。思いつかないときには、つぎの4つの切り口から考えます。
・悩みについてのセルフケアやチェックの方法、解決法
・悩みを解決するための知識
・悩みを解決するために役立つグッズや情報の紹介
・悩みに関するエピソード
3-3. 5ステップの構成で書く
ブログのネタが決まったら、つぎの5ステップの構成に沿って書きます。先ほどのAIDAと、基本的には同じ流れです。
① 問題提起:悩みの具体例や、実際の例を取りあげて、悩んでいるお客さまの注意をひきます。
② 問題の原因の指摘:その悩みの根本原因を伝えます。専門家ならではの視点とともに、お客さまの辛さに共感します。
③ 原因解決の考え方:根本原因を解決する方法を解説します。
④ 解決方法の紹介:お客さまの視点で、問題が解決する流れを伝えます。
⑤ まとめ:クールダウンしながら、商品やサービスについてさらりと紹介します。
3-4. SNSでシェアする
Facebook、Instagram、Twitterなど、あなたのお客さまがよく見ていると思われるSNSでシェアします。そうすることで、広いブログの海からあなたとつながっている方にお役立ちブログが伝わり、「いいね!」やシェアによって、直接つながっていない方へも波及することが期待できるでしょう。
まとめ

ここまで、あなただけが持つ「ほかにはない何か」を洗い出し、それを具体的な商品やサービスとして形にして、世の中に広めるための3ステップについてお伝えしてきました。
最後に、ひとつの質問をします。
あなたは、なぜ起業したいのでしょうか。
起業は格好よさそうだから。今の会社に不満があるから。稼げそうだから。
もしあなたが会社に勤めていて、そのような動機で起業を考えているのであれば、会社を辞めることはあまりお勧めできません。起業には、大きな失敗の危険性が必ず伴うからです。
もし起業するのであれば、作りあげた商品やサービスを、余暇でできる範囲で発信しながら、まずは副業のような形で始めるのがお勧めです。そして軌道に乗ったらその先を考えましょう。まずは生活の安定をはかり、そこをベースにしてものごとを考えていくことが大切です。
自分の持つ専門性を活かして、商品やサービスを世に送り出したい。会社に勤めることが難しく、起業するしか、生きていく道がない。お金と時間に余裕があり、いまの生活の中で無理なく自分を活かした仕事をしていきたい。
そんなあなたは、この記事を活用して、ぜひ新たな生き方や働き方を探してみてください。
すべての人が「わたしだからできること」を見出して、互いに提供しあえる社会になることを、心から願っています。
【参考資料】
・『繁盛サロンにするためのあなただけのオンリーワンメニューのつくり方』 穂口大悟著 同文館出版 2018年
・『新版 小さな会社☆儲けのルール』 竹田陽一・栢野克己著 フォレスト出版 2016